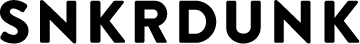『遊戯王』という名前は、今や世界的に通じるエンターテインメントの名称となっています。その中でも特に有名な名前として挙げられるカードの1枚が、今回紹介する「青眼の白龍」(ブルーアイズ・ホワイト・ドラゴン)です。
『遊戯王OCG』の歴史と共に様々な変遷を遂げてきた、この「青眼の白龍」というカードの活躍や変遷を紹介すると共に、現環境にて使っていきたいと考えているユーザーのための運用面について解説します。
TEXT:tomechu
「青眼の白龍」とは

| 種別 | 通常モンスター |
|---|---|
| レベル | 8 |
| 属性 | 光属性 |
| 種族 | ドラゴン族 |
| 攻撃力 | 3000 |
| 守備力 | 2500 |
| カードテキスト |
|---|
| 高い攻撃力を誇る伝説のドラゴン。どんな相手でも粉砕する、その破壊力は計り知れない。 |
1999年3月18日発売 の『STARTER BOX』に初収録されたモンスターカードです。ブルーアイズ以外では、モンスターをフィールドから破壊する効果を持った「サンダー・ボルト」が同時収録されています。
『TVアニメ遊戯王』では主人公「武藤遊戯」のライバルキャラ、「海馬瀬人」のエースモンスターとして登場したことにより、当時の視聴者に広く認知されました。アニメ上ではあまりにも強すぎたため、すぐ生産中止となり、世界で4枚しか出回っていないという”超レアカード”扱いになっています。
当初は「青眼の白龍」の所有者は4人いました。そのうちの1人、遊戯の祖父「武藤双六」の店で、「青眼の白龍」を海馬が見つけたことが物語の始まりです。その後、海馬が双六とのデュエルの末に入手した「青眼の白龍」を破り捨てたため、世界で3枚しか存在していません(その3枚はすべて海馬が入手しています)。
余談ですが、「ジャンプフェスタ1999」特典のシークレットレア「青眼の白龍」(通称:シクブル)は、現在でも100万円以上の価格で取引されています。
「青眼の白龍」の運用
「青眼の白龍」の運用に関しては、主に各種サポートカードを活用するデッキ構築をしていく形になります。
構築次第で様々なデッキの形があり、「青眼の白龍」に関するサポートカードや構築例については、次回以降詳しく書いていく予定です。まずは、この「青眼の白龍」に非常に強く関連するカードとして以下の2種類を紹介していきます。
「正義の味方 カイバーマン」

| 種別 | 効果モンスター |
|---|---|
| レベル | 3 |
| 属性 | 光属性 |
| 種族 | 戦士族 |
| 攻撃力 | 200 |
| 守備力 | 700 |
| カードテキスト |
|---|
| このカードをリリースして発動できる。手札から「青眼の白龍」1体を特殊召喚する。 |
「正義の味方 カイバーマン」は、「青眼の白龍」の使い手「海馬瀬人」をモチーフにしたカードです。 効果は非常にシンプルで、「このカードをリリースして発動できる。手札から「青眼の白龍」1体を特殊召喚する」となっています。
つまり、レベル8の最上級モンスターである「青眼の白龍」を、お手軽に特殊召喚できるカードになります。
このカードが発売された2004年当時は、すでに大型のモンスターを特殊召喚する方法は多数存在していましたが、「青眼の白龍」に注目したカードはほとんどありませんでした。そんななか、「青眼の白龍」にフィーチャーしているという点は、唯一無二と言えるでしょう。また、海馬瀬人がモチーフになっているというのも、ファンにとっては魅力の一つになっていますね。
「青き眼の乙女」

| 種別 | チューナー/効果モンスター |
|---|---|
| レベル | 1 |
| 属性 | 光属性 |
| 種族 | 魔法使い族 |
| 攻撃力 | 0 |
| 守備力 | 0 |
| カードテキスト |
|---|
|
このカード名の①②の効果は1ターンに1度、いずれか1つしか使用できない。 ①:フィールドの表側表示のこのカードが効果の対象になった時に発動できる。自分の手札・デッキ・墓地から「青眼の白龍」1体を選んで特殊召喚する。 ②:このカードが攻撃対象に選択された時に発動できる。その攻撃を無効にし、このカードの表示形式を変更する。その後、自分の手札・デッキ・墓地から「青眼の白龍」1体を選んで特殊召喚できる。 |
次に紹介するのは「青き眼の乙女」です。このカードは、アニメ『遊戯王』における重要キャラクター「キサラ」がモチーフになっているカードで、2013年発売の『ストラクチャーデッキ-青眼龍轟臨-』で登場しました。
能力を簡単に説明すると、このカードが効果の対象や攻撃対象になったら、「青眼の白龍」が出てくるというものです。当時の環境では、攻撃や対象を取らずにモンスターを除去することは難しい状況だったため、このカードに対して攻撃以外の対策を持たない場合、ほぼ確実に「青眼の白龍」が場に出てきます。また、このカードが《チューナーモンスター》であることも相まって、同時収録の《シンクロモンスター》である「蒼眼の銀龍」を出す際にも使用されていました。
最後に
今回は「青眼の白龍」についてご紹介しました。次回は「青眼の白龍」デッキの変遷について解説していきます。
関連記事
- リミットレギュレーション [2022年10月01日適用] 制限解除カードについての大会環境考察
- リミットレギュレーション [2022年10月01日適用] 準制限カードについての大会環境考察
- リミットレギュレーション [2022年10月01日適用] 新規禁止カードについての大会環境考察
引用元
yugioh-card.com
権利表記
©スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI